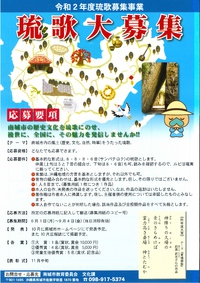2015年02月01日
第7話 垣花城跡
垣花(注①)城跡は主郭と二の郭に分かれ、南北に物見台を配し、城門は東を向きます。
築城年代は明らかになっていませんが、様々な説(注②)があります。
また、大城按司真武の妻は垣花城主の娘か妹であったとされることから、玉城グスクとの関係が伺えます(注③)。
城壁を見てみると全体的に野面積みで垂直に立ち上がる為、築城技術が未発達な時代に造られたと考えられますが、南側の物見台は切り石が積まれています。
以上のことから、グスク時代の早い時期に築城され、14世紀後半頃まで続いていたのではないかと考えられます。
周辺の垣花樋川(注④)遺跡や垣花洞穴遺跡からは貝塚時代の土器が出土しています。
このことから、垣花グスク築城以前からこの辺りには人々の生活があり、グスクの登場で大きく生活は変わったと考えられます。
また、グスク近くの垣花遺跡からは貝塚時代後期の土器、くびれ平底土器、グスク土器、カムイヤキ、中国産陶磁器、近世の陶器などが出土しています。
これは文明の到来を体感した人たちが生活していたということを表しています。
更に隣接して垣花製鉄遺跡があり鉄滓(てっさい)や炭、焼土などが出土しています。
文明を扱っていたということです。
注①垣花・・・明治までは和名盤(わな)と垣花に分かれておりグスク周辺の小字名は和名盤原(わなんばる)という
注②様々な説・・・ミントン按司の次男が築城したという説や、英祖王統二代目大成王から分かれた中城屋宜按司の築城という言い伝えがある
注③大城按司・・・大城グスクは玉城按司の次男が築城したとされ、真武という人物が按司の時に島添大里グスクと合戦(長堂原古戦場)し、もう一歩のところで旗持ちが旗を倒してしまい、大城グスクに残っていた家臣は城に火を着けてしまった
真武の子は幼少で垣花に隠れたが、追っ手が迫ったので小禄間切へ逃れた→那覇垣花の始まりと云われる
注④垣花樋川・・・名水百選にも選ばれている水場で、昔はトイから流れ出た水で野菜を洗ったり洗濯したりした(樋川の定義はトイがあること)

謎の多い垣花グスクですが本格的な調査はまだ行われていません
築城年代は明らかになっていませんが、様々な説(注②)があります。
また、大城按司真武の妻は垣花城主の娘か妹であったとされることから、玉城グスクとの関係が伺えます(注③)。
城壁を見てみると全体的に野面積みで垂直に立ち上がる為、築城技術が未発達な時代に造られたと考えられますが、南側の物見台は切り石が積まれています。
以上のことから、グスク時代の早い時期に築城され、14世紀後半頃まで続いていたのではないかと考えられます。
周辺の垣花樋川(注④)遺跡や垣花洞穴遺跡からは貝塚時代の土器が出土しています。
このことから、垣花グスク築城以前からこの辺りには人々の生活があり、グスクの登場で大きく生活は変わったと考えられます。
また、グスク近くの垣花遺跡からは貝塚時代後期の土器、くびれ平底土器、グスク土器、カムイヤキ、中国産陶磁器、近世の陶器などが出土しています。
これは文明の到来を体感した人たちが生活していたということを表しています。
更に隣接して垣花製鉄遺跡があり鉄滓(てっさい)や炭、焼土などが出土しています。
文明を扱っていたということです。
注①垣花・・・明治までは和名盤(わな)と垣花に分かれておりグスク周辺の小字名は和名盤原(わなんばる)という
注②様々な説・・・ミントン按司の次男が築城したという説や、英祖王統二代目大成王から分かれた中城屋宜按司の築城という言い伝えがある
注③大城按司・・・大城グスクは玉城按司の次男が築城したとされ、真武という人物が按司の時に島添大里グスクと合戦(長堂原古戦場)し、もう一歩のところで旗持ちが旗を倒してしまい、大城グスクに残っていた家臣は城に火を着けてしまった
真武の子は幼少で垣花に隠れたが、追っ手が迫ったので小禄間切へ逃れた→那覇垣花の始まりと云われる
注④垣花樋川・・・名水百選にも選ばれている水場で、昔はトイから流れ出た水で野菜を洗ったり洗濯したりした(樋川の定義はトイがあること)

謎の多い垣花グスクですが本格的な調査はまだ行われていません
Posted by 尚巴志活用MP at 13:59│Comments(2)
│【連載】南城市の歴史
この記事へのコメント
垣花グスクに強い関心をもっていましたが、さっぱりわからなくて困っていました。この説明が大助かりです。ありがとうございます。
Posted by 浅野誠 at 2015年02月01日 19:35
at 2015年02月01日 19:35
 at 2015年02月01日 19:35
at 2015年02月01日 19:35浅野先生、ありがとうございます。
できるだけ文献・伝承とモノの両サイドからロマンを引き出せればより南城市の歴史が面白くなるのではないかという考えで試みておりますが500字に収めるのが結構大変です。
読んで頂いているばかりかコメントまで頂きありがとうございます。
やり甲斐あります‼︎
できるだけ文献・伝承とモノの両サイドからロマンを引き出せればより南城市の歴史が面白くなるのではないかという考えで試みておりますが500字に収めるのが結構大変です。
読んで頂いているばかりかコメントまで頂きありがとうございます。
やり甲斐あります‼︎
Posted by 尚巴志活用MP at 2015年02月01日 20:46
at 2015年02月01日 20:46
 at 2015年02月01日 20:46
at 2015年02月01日 20:46