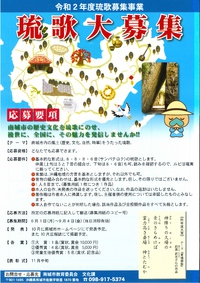2015年02月11日
第17話 廃藩置県と人の流れ
1609年に薩摩の島津軍が琉球へ侵攻した事件(注①)をきっかけに薩摩の琉球支配が開始されます。
この頃の王国の財政は厳しく、薩摩の利権も絡んだことで貿易の形も変わり経費がかさんで、納税者である農民は大変疲弊していました。
17世紀から18世紀にかけて羽地朝秀や蔡温によって王政の改革が行われましたが、王政終末には富裕層と貧農層の2極化を生むことになりました。
そして1879年、琉球処分(注②)によって沖縄県となります。
その後、1908年には佐敷、知念、玉城、大里の村政がスタートします。
番所を利用した小学校(注③)もつくられました。
置県後に首里や那覇から田舎下りして農業を始める士族もかなりいました。
この人たちは既存の集落の離れを開墾して屋取(ヤードゥイ)集落(注④)を形成し、農家から請け負った小作などを行って生活していました。
県は農業政策に力を入れ、増産競争を取り入れるために農業の優劣を競う原山勝負を行いました。
また、それに伴った馬勝負、角力、畜産の奨励を行う闘牛などが各地で催されるようになり、馬場である「ウマイー」(注⑤)はほとんどの農村にありましたし、闘牛場(注⑥)も佐敷、知念地域にありました。
1914年には軽便鉄道(注⑦)が開通し、現在の南城市では与那原線の大里駅と糸満線の稲嶺駅があり、交通と物流が発達しました。
また、1903年から移民(注⑧)が開始され、南城市ではハワイを中心に4450名が移民している。
注①島津侵攻・・・徳川家康は明との貿易を再開するために琉球を従わせたかったが、琉球側が応えることはなかった
そこで薩摩藩は幕府の許可を得て樺山久高を総大将に鉄砲隊をもって奄美大島、徳之島、沖永良部島を攻略し、上陸して今帰仁グスクを落とした
更に座喜味グスクを攻略して陸海から首里に入り尚寧王は開場して和議を申し入れた
尚寧は薩摩に抑留されその間に江戸へ上った
注②琉球処分・・・1871年の廃藩置県から遅れて1879年に琉球王国は沖縄県となった
当初は清との朝貢禁止や新暦の採用、王の上京が求められていたが交渉が難航し王国内も意見が割れたため、琉球処分官の松田道之は軍隊と警察で脅した
注③小学校・・・1880年に大里小学校、1882年に玉城小学校と佐敷小学校、1883年に知念小学校が創られた
注④屋取集落・・・兼久、伊原、仲伊保、冨祖崎、福原、古堅(大部分)、島袋(一部)、銭又、親慶原、喜良原、新原、船越(一部)、久原、海野、知名(一部)、吉富など
現在琉球ゴルフ倶楽部となっている場所にも与那川や上洲口、新川などの屋取集落があった
注⑤ウマイー・・・現在各集落にウマイーと呼ばれる広場があるが、これはその由来である
上洲口、津波古、新里、佐敷、手登根、外間などは戦後まで残っていた。
注⑥闘牛場・・・久原、佐敷、手登根、伊原では盛んに行われていた
注⑦軽便鉄道・・・与那原線は那覇駅→古波蔵駅→真玉橋駅→国場駅→一日橋駅→南風原駅→宮平駅→大里駅→与那原駅、糸満線は上記国場駅から別れ、津嘉山駅→山川駅→喜屋武駅→稲嶺駅→屋宜原駅→東風平駅→世名城駅→高嶺駅→兼城駅→糸満駅
他に嘉手納線がある
注⑧移民・・・戦前、南城市にあたる地域からは16国・地域へ送り出された
ハワイやペルーのプランテーションにおける重労働に従事し蓄財した
昭和恐慌時代にはその送金が県財政に大きく貢献した

琉球ゴルフ倶楽部内にあった屋取集落「新川」の拝所
残された拝所では毎年旧暦の十五夜に子孫らによって拝みが行われている
この頃の王国の財政は厳しく、薩摩の利権も絡んだことで貿易の形も変わり経費がかさんで、納税者である農民は大変疲弊していました。
17世紀から18世紀にかけて羽地朝秀や蔡温によって王政の改革が行われましたが、王政終末には富裕層と貧農層の2極化を生むことになりました。
そして1879年、琉球処分(注②)によって沖縄県となります。
その後、1908年には佐敷、知念、玉城、大里の村政がスタートします。
番所を利用した小学校(注③)もつくられました。
置県後に首里や那覇から田舎下りして農業を始める士族もかなりいました。
この人たちは既存の集落の離れを開墾して屋取(ヤードゥイ)集落(注④)を形成し、農家から請け負った小作などを行って生活していました。
県は農業政策に力を入れ、増産競争を取り入れるために農業の優劣を競う原山勝負を行いました。
また、それに伴った馬勝負、角力、畜産の奨励を行う闘牛などが各地で催されるようになり、馬場である「ウマイー」(注⑤)はほとんどの農村にありましたし、闘牛場(注⑥)も佐敷、知念地域にありました。
1914年には軽便鉄道(注⑦)が開通し、現在の南城市では与那原線の大里駅と糸満線の稲嶺駅があり、交通と物流が発達しました。
また、1903年から移民(注⑧)が開始され、南城市ではハワイを中心に4450名が移民している。
注①島津侵攻・・・徳川家康は明との貿易を再開するために琉球を従わせたかったが、琉球側が応えることはなかった
そこで薩摩藩は幕府の許可を得て樺山久高を総大将に鉄砲隊をもって奄美大島、徳之島、沖永良部島を攻略し、上陸して今帰仁グスクを落とした
更に座喜味グスクを攻略して陸海から首里に入り尚寧王は開場して和議を申し入れた
尚寧は薩摩に抑留されその間に江戸へ上った
注②琉球処分・・・1871年の廃藩置県から遅れて1879年に琉球王国は沖縄県となった
当初は清との朝貢禁止や新暦の採用、王の上京が求められていたが交渉が難航し王国内も意見が割れたため、琉球処分官の松田道之は軍隊と警察で脅した
注③小学校・・・1880年に大里小学校、1882年に玉城小学校と佐敷小学校、1883年に知念小学校が創られた
注④屋取集落・・・兼久、伊原、仲伊保、冨祖崎、福原、古堅(大部分)、島袋(一部)、銭又、親慶原、喜良原、新原、船越(一部)、久原、海野、知名(一部)、吉富など
現在琉球ゴルフ倶楽部となっている場所にも与那川や上洲口、新川などの屋取集落があった
注⑤ウマイー・・・現在各集落にウマイーと呼ばれる広場があるが、これはその由来である
上洲口、津波古、新里、佐敷、手登根、外間などは戦後まで残っていた。
注⑥闘牛場・・・久原、佐敷、手登根、伊原では盛んに行われていた
注⑦軽便鉄道・・・与那原線は那覇駅→古波蔵駅→真玉橋駅→国場駅→一日橋駅→南風原駅→宮平駅→大里駅→与那原駅、糸満線は上記国場駅から別れ、津嘉山駅→山川駅→喜屋武駅→稲嶺駅→屋宜原駅→東風平駅→世名城駅→高嶺駅→兼城駅→糸満駅
他に嘉手納線がある
注⑧移民・・・戦前、南城市にあたる地域からは16国・地域へ送り出された
ハワイやペルーのプランテーションにおける重労働に従事し蓄財した
昭和恐慌時代にはその送金が県財政に大きく貢献した

琉球ゴルフ倶楽部内にあった屋取集落「新川」の拝所
残された拝所では毎年旧暦の十五夜に子孫らによって拝みが行われている
Posted by 尚巴志活用MP at 01:15│Comments(0)
│【連載】南城市の歴史