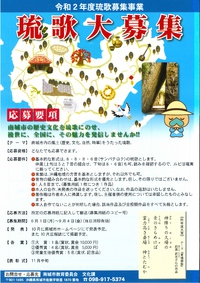2015年02月05日
第11話 佐敷城跡
12世紀頃から現在内原の殿がある広場あたりで人々の生活が始まります。
この頃は周辺の集落(注①)とかかわりを持っていました。
そこからは鍛冶を行っていた跡も発見されています。
13世紀には現在上グスクの嶽がある平場まで範囲を拡大し土木工事(注②)が施され始めました。
14世紀中頃から15世紀前半にかけて、佐敷上グスクは最盛期を迎えます。
現在つきしろの宮(注③)がある3つの曲輪を主体として東は苗代殿遺跡(注④)、西はタキノー丘陵(注⑤)や主体部分を防御する平場群(注⑥)まで拡がります。
また、この時期に縄張りにおいて美里殿遺跡(注⑦)を取り込み切岸などの整備が行われました。
遺物も多く出土し、中国産青磁の無文外反碗や、タイ産の無釉陶器、鉄絵壷(注⑧)などの出土遺物から独自の交易ルートを持っていたことが伺えます。
グスクの周辺については発掘調査で炭化米が出土していることから集落とともに稲作が広がっていたであろうことが想定されます。
港については遺跡周辺で確認されていないことから自然の浜を利用して交易を行っていた可能性があります。
最盛期は思紹・尚巴志が生きた時代です。
15世紀以降は祭祀儀礼(注⑨)が中心となり、現代に至ります。
注①集落•••下代原遺跡という集落跡で佐敷小学校の上方
注②土木工事•••平場造成、切岸、柵列を行った
土地を平らに整地し段々状にして郭をつくり貼り石状石列や柵列を施して強度と防御機能を増した
注③つきしろの宮•••後世に血縁組織によって造られた神社→第一尚氏が祀られている
注④苗代殿遺跡•••苗代大屋(思紹)の屋敷跡があったとされる遺跡
グスク的構造を持ち切岸や平場造成が行われている
つきしろの岩と井、苗代殿などがある
注⑤タキノー丘陵•••現在は水道タンクが設置されている丘陵で中城湾や島添大里グスクを望むことができ当時の雰囲気を味わえる
注⑥平場群•••現在はその地形を利用して畑が営まれている
史跡の構造を利用して農業を行う形態も珍しい
注⑦美里殿遺跡•••尚巴志の母の父である美里の子が住んでいたとされる場所
美里殿や美里井などがある
注⑧遺物…中国産青磁の無文外反碗は佐敷タイプと呼ばれるほど珍しく、他の遺跡ではあまり出土していないが糸数城跡では出土している
タイ産の無釉陶器は半練土器とも呼ばれ褐釉陶器などとともに東南アジア交易の主流商品
鉄絵壷は中国の磁州窯で焼かれた壷で鉄を溶かして全体に塗り削り取っていくものと書き込んでいくものの2種類がある大変貴重な遺物
注⑨祭祀儀礼…佐敷上グスクの嶽と新里の場天御嶽は国王の行幸である東御周りの拝所である

佐敷上グスクは何も遺っていないという人もいますがまったくそんなことありません
この頃は周辺の集落(注①)とかかわりを持っていました。
そこからは鍛冶を行っていた跡も発見されています。
13世紀には現在上グスクの嶽がある平場まで範囲を拡大し土木工事(注②)が施され始めました。
14世紀中頃から15世紀前半にかけて、佐敷上グスクは最盛期を迎えます。
現在つきしろの宮(注③)がある3つの曲輪を主体として東は苗代殿遺跡(注④)、西はタキノー丘陵(注⑤)や主体部分を防御する平場群(注⑥)まで拡がります。
また、この時期に縄張りにおいて美里殿遺跡(注⑦)を取り込み切岸などの整備が行われました。
遺物も多く出土し、中国産青磁の無文外反碗や、タイ産の無釉陶器、鉄絵壷(注⑧)などの出土遺物から独自の交易ルートを持っていたことが伺えます。
グスクの周辺については発掘調査で炭化米が出土していることから集落とともに稲作が広がっていたであろうことが想定されます。
港については遺跡周辺で確認されていないことから自然の浜を利用して交易を行っていた可能性があります。
最盛期は思紹・尚巴志が生きた時代です。
15世紀以降は祭祀儀礼(注⑨)が中心となり、現代に至ります。
注①集落•••下代原遺跡という集落跡で佐敷小学校の上方
注②土木工事•••平場造成、切岸、柵列を行った
土地を平らに整地し段々状にして郭をつくり貼り石状石列や柵列を施して強度と防御機能を増した
注③つきしろの宮•••後世に血縁組織によって造られた神社→第一尚氏が祀られている
注④苗代殿遺跡•••苗代大屋(思紹)の屋敷跡があったとされる遺跡
グスク的構造を持ち切岸や平場造成が行われている
つきしろの岩と井、苗代殿などがある
注⑤タキノー丘陵•••現在は水道タンクが設置されている丘陵で中城湾や島添大里グスクを望むことができ当時の雰囲気を味わえる
注⑥平場群•••現在はその地形を利用して畑が営まれている
史跡の構造を利用して農業を行う形態も珍しい
注⑦美里殿遺跡•••尚巴志の母の父である美里の子が住んでいたとされる場所
美里殿や美里井などがある
注⑧遺物…中国産青磁の無文外反碗は佐敷タイプと呼ばれるほど珍しく、他の遺跡ではあまり出土していないが糸数城跡では出土している
タイ産の無釉陶器は半練土器とも呼ばれ褐釉陶器などとともに東南アジア交易の主流商品
鉄絵壷は中国の磁州窯で焼かれた壷で鉄を溶かして全体に塗り削り取っていくものと書き込んでいくものの2種類がある大変貴重な遺物
注⑨祭祀儀礼…佐敷上グスクの嶽と新里の場天御嶽は国王の行幸である東御周りの拝所である
佐敷上グスクは何も遺っていないという人もいますがまったくそんなことありません
Posted by 尚巴志活用MP at 08:53│Comments(0)
│【連載】南城市の歴史