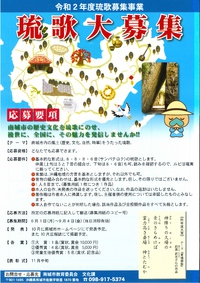2015年02月04日
第10話 島添大里城跡と「下の世の主」
発掘調査の結果によると、12世紀頃に現在パークゴルフ場となっている地区(注①)で人々の生活が始まったと考えられます。
13世紀頃になると集落(注②)が形成されはじめ、いよいよグスクとしての機能が整い始めます。
14世紀頃には城壁が積み上げられ始め、主郭に正殿や御庭が造成されました。
最盛期(注③)は14世紀後半から15世紀頃で「下の世の主」と呼ばれる人物が現在の南城市と与那原町(注④)に当たる地域を治めていたと云われています。グスクは連郭式で規模は30,000㎡を超え南部最大級でした。正殿は首里城に次ぐ大きさを誇ります。
港は当添港や場天港で、発掘調査によると輸入陶磁器や金属製品(注⑤)などが出土しており、交易で栄えた様子がうかがえると共に、三山分立時代における山南城(注⑥)だったという説を後押しする繁栄ぶりが見えてきました。
しかし、栄華は突如として崩れ去ります。1402年に佐敷から起こった尚巴志が島添大里按司を倒し三山統一に乗り出します。
島添大里グスクはその拠点となり、首里城が整備された後はその離宮となりました。
城内で見つかった尚泰久の銘が入りの雲板(注⑦)がそれを示しています。
島おそい(注⑧)の按司は遠くに中山城を見据えながらどのような夢を描いていたのでしょうか。
注①パークゴルフ場•••大里城趾公園となっていてパークゴルフ場の下には真手川原遺跡という生産遺跡(耕作跡)が残っている
注②集落•••現在体験交流センターが建てられている場所は島添大里グスク南遺跡という集落跡があり多くの柱跡や輸入陶磁器などが出土している
注③最盛期•••元々この地を治めていた按司はギリムイグスクにいたが島添大里グスクが築城されてからは南西側の物見台となった
また、北東側の物見台はミーグスクがあり掘立柱建物跡が見つかっている
正殿は礎石立ちで基壇上に築かれている
外郭は石積みで仕切られる三連郭になっていたと考えられており、主郭から扇状に広がっている
保水に優れた地形でチチンガーをはじめ井泉がいくつか存在する
注④南城市と与那原町•••東四間切(あがりゆまじり)といわれる
注⑤金属製品•••城内にカニマン御嶽という拝所があり、鍛冶屋を祀っているという
正殿跡から青銅製の金飾りなども出土しており金属製品の流通や金属文化の発達が見られる
注⑥山南城•••島尻大里グスク(糸満市在)という説もある
注⑦雲板•••仏教に係る道具でお寺などにあり叩いて合図をしたりする
注⑧島おそい•••「添」は「おそい」として「統べる」意味合い
浦添は「うらおそい」とされ浦々を統べるということ
首里城正殿は百浦おそい(百添)と呼ばれていた
「添」という言葉は簡単に当てがわれる比喩表現ではないようである
このことからも島添大里グスクの栄華が想像できる

島添大里グスクは当時南部における経済の中心地でした
13世紀頃になると集落(注②)が形成されはじめ、いよいよグスクとしての機能が整い始めます。
14世紀頃には城壁が積み上げられ始め、主郭に正殿や御庭が造成されました。
最盛期(注③)は14世紀後半から15世紀頃で「下の世の主」と呼ばれる人物が現在の南城市と与那原町(注④)に当たる地域を治めていたと云われています。グスクは連郭式で規模は30,000㎡を超え南部最大級でした。正殿は首里城に次ぐ大きさを誇ります。
港は当添港や場天港で、発掘調査によると輸入陶磁器や金属製品(注⑤)などが出土しており、交易で栄えた様子がうかがえると共に、三山分立時代における山南城(注⑥)だったという説を後押しする繁栄ぶりが見えてきました。
しかし、栄華は突如として崩れ去ります。1402年に佐敷から起こった尚巴志が島添大里按司を倒し三山統一に乗り出します。
島添大里グスクはその拠点となり、首里城が整備された後はその離宮となりました。
城内で見つかった尚泰久の銘が入りの雲板(注⑦)がそれを示しています。
島おそい(注⑧)の按司は遠くに中山城を見据えながらどのような夢を描いていたのでしょうか。
注①パークゴルフ場•••大里城趾公園となっていてパークゴルフ場の下には真手川原遺跡という生産遺跡(耕作跡)が残っている
注②集落•••現在体験交流センターが建てられている場所は島添大里グスク南遺跡という集落跡があり多くの柱跡や輸入陶磁器などが出土している
注③最盛期•••元々この地を治めていた按司はギリムイグスクにいたが島添大里グスクが築城されてからは南西側の物見台となった
また、北東側の物見台はミーグスクがあり掘立柱建物跡が見つかっている
正殿は礎石立ちで基壇上に築かれている
外郭は石積みで仕切られる三連郭になっていたと考えられており、主郭から扇状に広がっている
保水に優れた地形でチチンガーをはじめ井泉がいくつか存在する
注④南城市と与那原町•••東四間切(あがりゆまじり)といわれる
注⑤金属製品•••城内にカニマン御嶽という拝所があり、鍛冶屋を祀っているという
正殿跡から青銅製の金飾りなども出土しており金属製品の流通や金属文化の発達が見られる
注⑥山南城•••島尻大里グスク(糸満市在)という説もある
注⑦雲板•••仏教に係る道具でお寺などにあり叩いて合図をしたりする
注⑧島おそい•••「添」は「おそい」として「統べる」意味合い
浦添は「うらおそい」とされ浦々を統べるということ
首里城正殿は百浦おそい(百添)と呼ばれていた
「添」という言葉は簡単に当てがわれる比喩表現ではないようである
このことからも島添大里グスクの栄華が想像できる
島添大里グスクは当時南部における経済の中心地でした
Posted by 尚巴志活用MP at 08:34│Comments(0)
│【連載】南城市の歴史