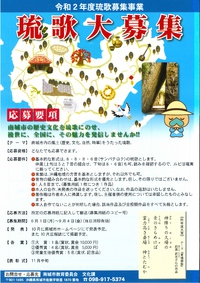2015年01月28日
第3話 農耕の始まり
11世紀頃、琉球を取り巻く貿易の状況は変化を見せてきます。
琉球では、これまで「くびれ平底土器」と呼ばれる貝塚時代後期の土器から「グスク土器」と呼ばれる新しい様式の土器に変わってきます。
また、輸入品には中国製の玉縁白磁碗や徳之島のカムィヤキ、長崎産の滑石製石鍋などがあり、「グスク土器」はこれらを模して作られたと考えられています。
これらの文明を持ち込んだ人々は一体どのような人たちで元々「くびれ平底土器」を使っていた人たちはどうなってしまったのでしょうか。
そしていよいよ琉球に農耕が入ってきます。
鉄の農具が少ない時代、農業は1人でできるものではありません。
それはすなわち共同体の始まりであるとも言えます。
南城市においては、島添大里城跡に隣接する真手川原遺跡(注①)の調査で12世紀頃の耕作跡が発見されました。
遺跡は琉球石灰岩台地の縁辺にあり、わずかですが稲や麦に類する植物が出土していることから麦畑と稲作を営んでいた可能性があります。
また、受水走水やウファカルなどの穀物神話(注②)は琉球開闢神話と併せて文明の大転換を表しているのかもしれません。
なぜなら両方とも稲作を大規模に行うにはもってこいの場所だからです。
注①真手川原遺跡・・・現在大里城趾公園パークゴルフ場の地中にある生産遺跡
注②穀物神話・・・『中山世鑑』では阿摩美久が天に上り五穀の種子を乞うて、麦、粟、豆、黍(キビ)の数種を初めて久高島にまき、稲は知念大川の後ろ(ウファカル)と玉城ヲケミゾ(受水走水)に植えたとされる
受水走水については暴風により落ちてきた鶴が稲穂をくわえていてそれを阿摩美津という人が御穂田(みーふーだ)に移し植えたとの伝承もある

狩猟採集からわざわざ農業を始めた理由は統治国家にするためか??
琉球では、これまで「くびれ平底土器」と呼ばれる貝塚時代後期の土器から「グスク土器」と呼ばれる新しい様式の土器に変わってきます。
また、輸入品には中国製の玉縁白磁碗や徳之島のカムィヤキ、長崎産の滑石製石鍋などがあり、「グスク土器」はこれらを模して作られたと考えられています。
これらの文明を持ち込んだ人々は一体どのような人たちで元々「くびれ平底土器」を使っていた人たちはどうなってしまったのでしょうか。
そしていよいよ琉球に農耕が入ってきます。
鉄の農具が少ない時代、農業は1人でできるものではありません。
それはすなわち共同体の始まりであるとも言えます。
南城市においては、島添大里城跡に隣接する真手川原遺跡(注①)の調査で12世紀頃の耕作跡が発見されました。
遺跡は琉球石灰岩台地の縁辺にあり、わずかですが稲や麦に類する植物が出土していることから麦畑と稲作を営んでいた可能性があります。
また、受水走水やウファカルなどの穀物神話(注②)は琉球開闢神話と併せて文明の大転換を表しているのかもしれません。
なぜなら両方とも稲作を大規模に行うにはもってこいの場所だからです。
注①真手川原遺跡・・・現在大里城趾公園パークゴルフ場の地中にある生産遺跡
注②穀物神話・・・『中山世鑑』では阿摩美久が天に上り五穀の種子を乞うて、麦、粟、豆、黍(キビ)の数種を初めて久高島にまき、稲は知念大川の後ろ(ウファカル)と玉城ヲケミゾ(受水走水)に植えたとされる
受水走水については暴風により落ちてきた鶴が稲穂をくわえていてそれを阿摩美津という人が御穂田(みーふーだ)に移し植えたとの伝承もある
狩猟採集からわざわざ農業を始めた理由は統治国家にするためか??
Posted by 尚巴志活用MP at 08:40│Comments(0)
│【連載】南城市の歴史