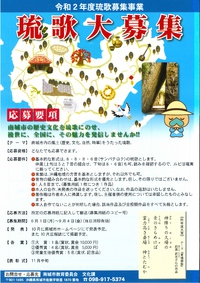2015年01月28日
第2話 琉球開闢神話
玉城・知念の海はイノーと呼ばれるさんご礁の浅瀬が広がっており、大型の船で陸地へ近づくのは容易ではありません。
しかし、『おもろそうし』にミオ(水路)について歌ったものがあり、当時の人々はイノーの切れ目をぬって陸地と沖を往来していたと考えられます。
伝承によると海の彼方にあるニライカナイからアマミキヨがやってきて最初に降り立ったのがヤハラヅカサ(注①)であると言います。
その前に久高島に降り立って島づたいにヤハラヅカサへ来たという説もあります。
その後、浜川御嶽近くの岩穴で仮住まいをし、ミントングスクを築いたとされます。
グスクの構築に繋がるこの神話は、新たな文明の到来を意味する可能性もあります。
『中山世鑑』によると、天帝に命じられて降臨した阿摩美久(アマミク)が七御嶽(注②)を作り、天帝の御子(男女)を降臨させ三男二女(注③)が生まれたとされています。
『琉球神道記』では、天から降りた男女をシネリキュ(男)、アマミキュ(女)とし、三子(注④)を産んだとしています。
南城市が聖地とされているのはこれらの神話によるものです。
注①ヤハラヅカサ・・・『琉球国由来記』には濱川(浜川御嶽)の神名をヤハラヅカサ潮バナツカサノ御イベとしている
注②七御嶽・・・辺戸の安須森、今帰仁のカナヒヤブ(受剣岩)、知念森(知念グスク一帯)・斎場御嶽、藪薩の浦原(百名団地付近から新原一帯)、玉城アマツヅ(玉城城跡の主郭)、久高コバウ森(クボウ御嶽)、首里森・真玉森(首里城内)
三男二女・・・長男が国の主(天孫氏)、二男が諸侯の始まり、三男が百姓の始まり、長女が君々(高級神女)の始まり、次女がノロの始まり
三子・・・一人目は所々の主の始まり、二人目はノロの始まり、三人目は土民の始まり

ヤハラヅカサに降り立った神は天から来たのか海の彼方から来たのか•••
しかし、『おもろそうし』にミオ(水路)について歌ったものがあり、当時の人々はイノーの切れ目をぬって陸地と沖を往来していたと考えられます。
伝承によると海の彼方にあるニライカナイからアマミキヨがやってきて最初に降り立ったのがヤハラヅカサ(注①)であると言います。
その前に久高島に降り立って島づたいにヤハラヅカサへ来たという説もあります。
その後、浜川御嶽近くの岩穴で仮住まいをし、ミントングスクを築いたとされます。
グスクの構築に繋がるこの神話は、新たな文明の到来を意味する可能性もあります。
『中山世鑑』によると、天帝に命じられて降臨した阿摩美久(アマミク)が七御嶽(注②)を作り、天帝の御子(男女)を降臨させ三男二女(注③)が生まれたとされています。
『琉球神道記』では、天から降りた男女をシネリキュ(男)、アマミキュ(女)とし、三子(注④)を産んだとしています。
南城市が聖地とされているのはこれらの神話によるものです。
注①ヤハラヅカサ・・・『琉球国由来記』には濱川(浜川御嶽)の神名をヤハラヅカサ潮バナツカサノ御イベとしている
注②七御嶽・・・辺戸の安須森、今帰仁のカナヒヤブ(受剣岩)、知念森(知念グスク一帯)・斎場御嶽、藪薩の浦原(百名団地付近から新原一帯)、玉城アマツヅ(玉城城跡の主郭)、久高コバウ森(クボウ御嶽)、首里森・真玉森(首里城内)
三男二女・・・長男が国の主(天孫氏)、二男が諸侯の始まり、三男が百姓の始まり、長女が君々(高級神女)の始まり、次女がノロの始まり
三子・・・一人目は所々の主の始まり、二人目はノロの始まり、三人目は土民の始まり

ヤハラヅカサに降り立った神は天から来たのか海の彼方から来たのか•••
Posted by 尚巴志活用MP at 08:32│Comments(0)
│【連載】南城市の歴史