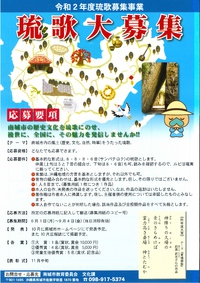2014年09月02日
日本生活指導学会に参加‼︎
去る8月29日(金)に沖縄大学で日本生活指導学会第32回研究大会が開催されました。
同日15時から行われた課題研究においては「青年期生活指導実践ー他者と共に生きることの学び」と題し二者の事例報告とフリーディスカッションが行われました。
事例報告は私が「南城市における若者の現状について」と題し、自信の親慶原青年会における実践からシュガーホール、尚巴志活用マスタープラン、南城市ミニバレー協会に関する取り組みを紹介し、エコミュージアムにおいて地域興しを担う若者・青年が活躍する可能性ということを着地点に話させて頂いたのと、特定非営利活動法人 社会理論・動態研究所の打越正行氏により「暴力を統制するー沖縄の下層若者の生活実践からー」と題して3人の若者の生き方から、なぜ彼らが暴力という手法に頼るのか、そのバックボーンを探りつつ社会と彼らの関係について明らかにしつつ現状が報告されました。
枠組、環境、個へのアプローチ、セーフティネット、排他感、組織…などなどのキーワードを深めると共に、エコミュージアムに若者に関わってもらい、地域を興していくための課題に取り組んでいく必要があると感じました。
かなり多くのヒントを頂きました‼︎
非常に有意義な場をご紹介頂きました浅野誠先生をはじめ、日本生活指導学会の皆様、ありがとうございましたm(_ _)m

同日15時から行われた課題研究においては「青年期生活指導実践ー他者と共に生きることの学び」と題し二者の事例報告とフリーディスカッションが行われました。
事例報告は私が「南城市における若者の現状について」と題し、自信の親慶原青年会における実践からシュガーホール、尚巴志活用マスタープラン、南城市ミニバレー協会に関する取り組みを紹介し、エコミュージアムにおいて地域興しを担う若者・青年が活躍する可能性ということを着地点に話させて頂いたのと、特定非営利活動法人 社会理論・動態研究所の打越正行氏により「暴力を統制するー沖縄の下層若者の生活実践からー」と題して3人の若者の生き方から、なぜ彼らが暴力という手法に頼るのか、そのバックボーンを探りつつ社会と彼らの関係について明らかにしつつ現状が報告されました。
枠組、環境、個へのアプローチ、セーフティネット、排他感、組織…などなどのキーワードを深めると共に、エコミュージアムに若者に関わってもらい、地域を興していくための課題に取り組んでいく必要があると感じました。
かなり多くのヒントを頂きました‼︎
非常に有意義な場をご紹介頂きました浅野誠先生をはじめ、日本生活指導学会の皆様、ありがとうございましたm(_ _)m