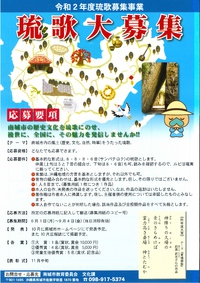› 尚巴志活用マスタープラン(沖縄県南城市) › 半島芸術祭コラボ企画「注文の多い料理店」 › エコミュージアム › 尚巴志の普及・啓発・情報発信 › イベント情報 › 『注文の多い料理店』•••?そうだ!図書館へ行ってみよう‼︎‼︎
› 尚巴志活用マスタープラン(沖縄県南城市) › 半島芸術祭コラボ企画「注文の多い料理店」 › エコミュージアム › 尚巴志の普及・啓発・情報発信 › イベント情報 › 『注文の多い料理店』•••?そうだ!図書館へ行ってみよう‼︎‼︎2014年10月26日
『注文の多い料理店』•••?そうだ!図書館へ行ってみよう‼︎‼︎
1924年に出版された宮沢賢治の短編集のタイトルでもあり、その中に入っている童話の名称でもあります。
南城市の各図書館にありますので是非一度読んでみて下さい。
今回は各館でポップを作って特集してくれてますよ〜♫

数年前、演出家の小池博史さんがご自身のカンパニーであるパパ・タラフマラを解散し、ブリッジプロジェクトを立ち上げて最初の作品がこの「注文の多い料理店」でした。
事前に読んでみて、童話なのですが、深いストーリーを探っていくと•••ちょっと怖いなという印象です。
ただ、舞台で観ると深く考えさせられました。そう、大人にとっては警笛だったりします•••。
子ども達にとっては動きや衣装チェンジ、仮面を用いたりして結構楽しめると思います。
効果音や照明演出も、舞台道具も独特な世界観で面白いです。
※ここからはネタバレ注意‼︎‼︎
ホームページのイントロダクションは以下の通り。
演出家・小池博史の、パパ・タラフマラ解散後一作目は名作童話"注文の多い料理店"。演劇であり、ダンスでもある。人間でありながら、森の動物でもある。喜劇であり、悲劇である。世界で評価される小池博史の深遠なる童話作品!おとなも、こどもも楽しめる、ダンス演劇!あっというまに時間も国も飛び越える!
あらすじは以下の通り。
宮沢賢治の名作童話「注文の多い料理店」。山奥に狩りの楽しみを求めてやってきた青年紳士たちは嵐に遭い、這々の体で、発見したのが「西洋料理店 山猫軒」。そこは不思議な「注文の多い料理店」だった。次々と注文を出されて、はじめは意気揚々と要求に応える紳士達だったが、不思議な動物達の誘いを甘受しつつ、いくつもの部屋を通り抜けていくとそこには大きな得体の知れない“なにか”が潜んでいた。 それは一体何であるのか、そして私たち人間はそれとどのように対峙すべきなのか。 紳士達がみた風景は人間の存在そのものを問いかける。
(小池博史ブリッジプロジェクトのHPより抜粋)
小池博史さんからのメッセージです。
2012年5月末日にパパ・タラフマラは解散し、6月に流山のみで実施した「小池博史ブリッジプロジェクト」の第一作目。やっと東京に戻りました。2011年3月11日以降、自問自答し続けては、30年続けた組織を解体させ、真っ先に生み出した作品です。人間と自然の関係を問い直し、私たち自身に向かっての回答としてではなく、疑問として提示しています。 今、人間とって必要なのは胸を張れる輝かしさです。人としての源泉を、全感覚を通して探求することで、初めて次が見えてきます。その源泉を問うのが、悲しく、怖く、楽しく、可笑しい「注文の多い料理店」。ご来店くださいませ。
(小池博史ブリッジプロジェクトのHPより抜粋)
なぜ、今宮沢賢治作品なのか?
本作品は2010年12月、前作の全国ツアーにて岩手県北上市に訪れた際に端を発します。澄み渡りピンと張った空気と、何かを秘めた様な美しい風景に宮沢賢治を改めて感じ、その源泉を見たような気がしました。人間とは何か?人間は自然とどのような関係性を結べばいいのか?という観点に立ち帰るに、宮沢賢治は素晴らしい先人として存在しています。そこで、彼の代表作である「注文の多い料理店」を、まったく新しい意匠で作品化し、かつ、手軽に公演可能とするものにしようと思いました。
その3ヶ月後、東北関東大震災が発生しました。あの美しい風景を自然の猛威は一瞬にして奪い去り、人智の結晶であるはずの文明を飲み込んでいきました。巨大地下プレートが交錯する日本列島に於いて、今、私達はどのように自然と共に生きればいいか、問い返されています。 宮沢賢治の童話を作品化することで、改めて深く人と自然について考えたいと思っています。
(小池博史ブリッジプロジェクトのHPより抜粋)
↓↓ホームページはこちらから‼︎
http://kikh.com/chumon/index.html
↓↓作家の田口ランディさんの感想もあります。
http://kikh.com/chumon/review_randy.html
「山猫軒」のオーナー•••こんな感じでしょうか??(笑)

南城市の各図書館にありますので是非一度読んでみて下さい。
今回は各館でポップを作って特集してくれてますよ〜♫

数年前、演出家の小池博史さんがご自身のカンパニーであるパパ・タラフマラを解散し、ブリッジプロジェクトを立ち上げて最初の作品がこの「注文の多い料理店」でした。
事前に読んでみて、童話なのですが、深いストーリーを探っていくと•••ちょっと怖いなという印象です。
ただ、舞台で観ると深く考えさせられました。そう、大人にとっては警笛だったりします•••。
子ども達にとっては動きや衣装チェンジ、仮面を用いたりして結構楽しめると思います。
効果音や照明演出も、舞台道具も独特な世界観で面白いです。
※ここからはネタバレ注意‼︎‼︎
ホームページのイントロダクションは以下の通り。
演出家・小池博史の、パパ・タラフマラ解散後一作目は名作童話"注文の多い料理店"。演劇であり、ダンスでもある。人間でありながら、森の動物でもある。喜劇であり、悲劇である。世界で評価される小池博史の深遠なる童話作品!おとなも、こどもも楽しめる、ダンス演劇!あっというまに時間も国も飛び越える!
あらすじは以下の通り。
宮沢賢治の名作童話「注文の多い料理店」。山奥に狩りの楽しみを求めてやってきた青年紳士たちは嵐に遭い、這々の体で、発見したのが「西洋料理店 山猫軒」。そこは不思議な「注文の多い料理店」だった。次々と注文を出されて、はじめは意気揚々と要求に応える紳士達だったが、不思議な動物達の誘いを甘受しつつ、いくつもの部屋を通り抜けていくとそこには大きな得体の知れない“なにか”が潜んでいた。 それは一体何であるのか、そして私たち人間はそれとどのように対峙すべきなのか。 紳士達がみた風景は人間の存在そのものを問いかける。
(小池博史ブリッジプロジェクトのHPより抜粋)
小池博史さんからのメッセージです。
2012年5月末日にパパ・タラフマラは解散し、6月に流山のみで実施した「小池博史ブリッジプロジェクト」の第一作目。やっと東京に戻りました。2011年3月11日以降、自問自答し続けては、30年続けた組織を解体させ、真っ先に生み出した作品です。人間と自然の関係を問い直し、私たち自身に向かっての回答としてではなく、疑問として提示しています。 今、人間とって必要なのは胸を張れる輝かしさです。人としての源泉を、全感覚を通して探求することで、初めて次が見えてきます。その源泉を問うのが、悲しく、怖く、楽しく、可笑しい「注文の多い料理店」。ご来店くださいませ。
(小池博史ブリッジプロジェクトのHPより抜粋)
なぜ、今宮沢賢治作品なのか?
本作品は2010年12月、前作の全国ツアーにて岩手県北上市に訪れた際に端を発します。澄み渡りピンと張った空気と、何かを秘めた様な美しい風景に宮沢賢治を改めて感じ、その源泉を見たような気がしました。人間とは何か?人間は自然とどのような関係性を結べばいいのか?という観点に立ち帰るに、宮沢賢治は素晴らしい先人として存在しています。そこで、彼の代表作である「注文の多い料理店」を、まったく新しい意匠で作品化し、かつ、手軽に公演可能とするものにしようと思いました。
その3ヶ月後、東北関東大震災が発生しました。あの美しい風景を自然の猛威は一瞬にして奪い去り、人智の結晶であるはずの文明を飲み込んでいきました。巨大地下プレートが交錯する日本列島に於いて、今、私達はどのように自然と共に生きればいいか、問い返されています。 宮沢賢治の童話を作品化することで、改めて深く人と自然について考えたいと思っています。
(小池博史ブリッジプロジェクトのHPより抜粋)
↓↓ホームページはこちらから‼︎
http://kikh.com/chumon/index.html
↓↓作家の田口ランディさんの感想もあります。
http://kikh.com/chumon/review_randy.html
「山猫軒」のオーナー•••こんな感じでしょうか??(笑)